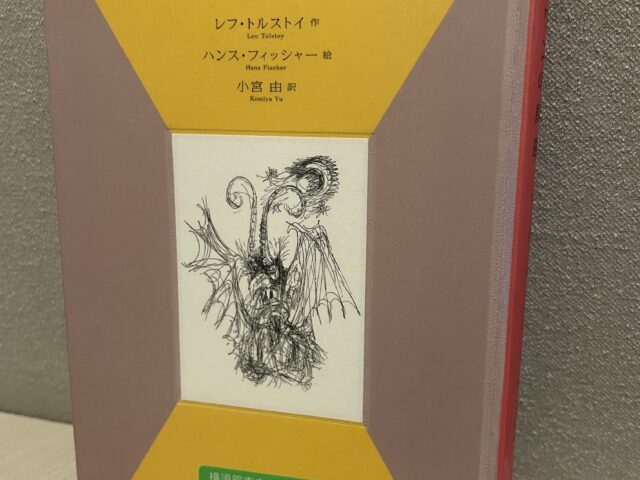生活保護受給者の転居問題。理由は家の老朽化。転居費用捻出は家主か福祉事務所か、はたまた受給者本人か―②
家主さんは「敷金プラス家賃2か月分を出しましょう。」と提案してきた。本当は転居費用を全部もってくれると、嬉しかったのだが、そこまでは残念ながら届かなかった。その旨を書いた書面を作成してもらいそれを福祉事務所へ提出した。そして、その材料を福祉事務所内で論議してもらった。
結果、「Zさん、新しいアパート探しをはじめてください。」と福祉事務所の回答が来た。
つまり、これは転居費用の差額分は福祉事務所が出すということ。アパート探しはZさんの自助努力となる。まだまだ途上ではあるが、結構長い道のりだった。これで、展望が開けた思いだ。
この場合、福祉事務所は生活保護受給者であるZさんの「生存権」を考えなければならない。「健康で文化的な最低限度の生活」の維持のために福祉事務所はZさんを支援しなければならないのだ。しかし、福祉事務所はみずから進んで家主と折衝しようとはしなかった。しなかったというより、ここは公の限界点だ。アパート探しにも手を貸すことはできない、これが基本原則なんだと思う。
今回のようなケースは家主も折れ、福祉事務所も折れ、両者の折衷案のようなところでまとまった。大きな災害となることもなく、老朽化した家でもなんとか住んでこられたので、大したことにならなかったが、この問題は重大な問題を孕んでいるともいえると思う。家主も福祉事務所も両者とも引かない姿勢の中で、何年もこれが続けば、店子であるZさんは憔悴しきってしまっただろう。
以前にも生活保護の扶養義務の問題をこのブログでも書いたけれど、どうしてもっと裁量権を行使しないのかと思うのである。自治体の福祉事務所は県の担当課や厚生労働省の顔色ばかりをうかがうのではなくて、もっと柔軟な使い勝手の良い制度に、自らが実践の中で改善していくべきなんだと思う。
先日も「横須賀 生活と健康を守る会 準備会」の中で、参加者が縦横に論議していたが、生活保護制度の各局面における時々の対応は、どの立場でどこを観て対応するかで、全く違ったものになるということだ。今回のことを教訓にして、さらに制度を後退させない努力を仲間としていきたい。