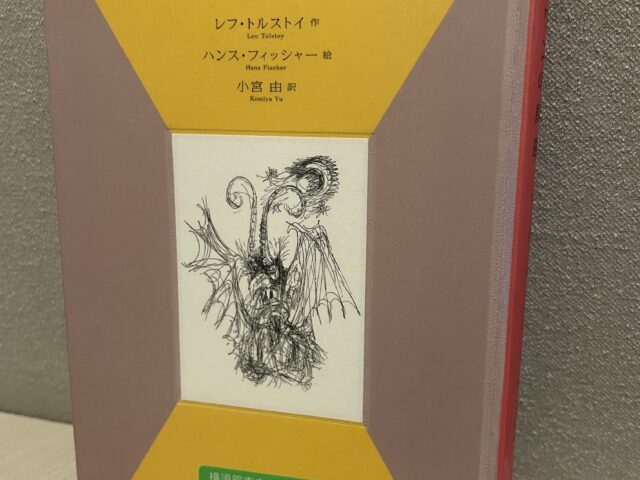違和感を覚える行政が流布する「生涯現役」という言葉
教育福祉分科会と常任員会の議案審査がはじまった。昨年からの市の施策の3本柱である
①子育て教育施策の充実
②生涯現役社会の実現
③地域経済の活性化
これらの施策の2年目の予算案が出され、本格的に2015年度はどうするのかということを審査している。昨年はそれほど違和感を覚えなかったが、2番目の「生涯現役」という言葉にはどうもしっくりこない。市長は施政方針の中で、「本市は、すでに高齢者の人口割合が28%を超え、若年層が減少しています。超高齢社会を迎えた本市にとって、一人でも多くの市民の皆さまが、健康で生きがいを持ち、いつまでも活躍できる「生涯現役社会の実現」を目指すことは非常に重要です。」と述べた。
確かに40万横須賀市の首長にとって、高齢人口が増えていくということは、就労年齢層が減り、したがって税収も減る。病気になる市民が増えれば、国民健康保険の給付額も増える。自治体を切り盛りする側から考えれば、(もちろん、市民にとっても)何の施策も打たないということは、台風の前に、家屋や庭など周囲のチェックをして暴風雨への備えを何もしないのと同じことだ。だから、ラジオ体操やウォーキングで健康を維持する。特定検診を受けたり、各種がん検診をうけたり、生きがいづくりで市民大学講座やスポーツや文化活動のメニューを増やすというのは、良いことだと思う。というか、そういう施策に取り組むのは、これからの動向を考えるならば、むしろ必須だと思う。
それにしても、生涯現役とはなんだろうか。現役という言葉にどうもひっかかる。
「私は現役はもう終わり。これからはゆったり、のんびりやりたいんだ。」そういう人の意見はどうすればいいのか。そして、現役という言葉の中には、どうも何でもバリバリできる、若者なんぞにはまだ、負けないぞ!という感じが漂うのは、私の偏見だろうか。障害を持った人や、病気の人はどう評価されるのか。現役という言葉の響きには、「モノになる」とか「戦力になる」とか「まだ、引退していない」とか「自立している」とか「世話にならずに頑張っている」といったニュアンスを感じる。
しかも、この「生涯現役」はリタイアした年齢層の人々にだけ向けられたメッセージではなくて、若い世代や働き盛りの世代にも向けられているとのことである。若い世代のときから、ゆっくり刷り込んでいくということだろうか。寝たきりの人には寝たきりの人の1日、1週間、1か月、1年があるだろう。一人ひとりにクオリティ・オブ・ライフがある。それを行政が、わざわざ現役を推奨するのは大きなお世話ではないか。自分らしく生きられる社会こそが実現されるべきではないか。
うちで咲いたチューリップ(昨年)