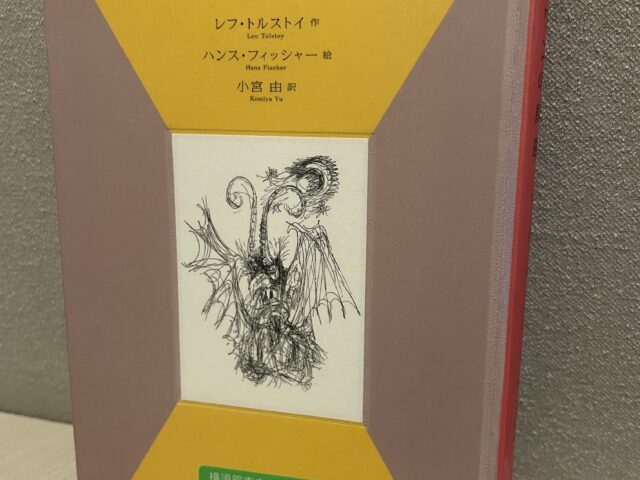いい加減、学べよ、人類!
昔はもっと環境のこと、食べ物のこと、洗剤やら電磁波やらそういうものに関心が高く批判的にとらえ、できるだけ暮らしから悪いものは排除しようという思いが強かった。環境問題のきっかけは高校の倫理社会だと思う。倫理社会の教師は私が鞄に友人からもらったか何かのキーホルダーをぶら下げていたら、それだけで職員室に私を呼び出し、反省しないからと言って職員室の前に正座を命じた。まったくあの日の出来事は今でも忘れない。あんな不条理なことってあるか。私はそれ以降、倫理社会の教師に対して「こいつを許すものか」と思い続けた。哲学や思想やそういうことを教えている立場なのに、杓子定規に校則をあてはめたあのやり口はおよそ、人を導くような器ではない。青い私はそう思いつづけた。
しかし、そんな倫理社会の教師にも良いところがあった。それが環境問題を教えてくれた点だ。フロンによってオゾン層が破壊され地球上に紫外線が降り注ぐとか、酸性雨の話だとか、アメリカの副大統領アル・ゴア氏の「不都合うな真実」だとかそんな大事な話を授業で聴いて(いや、後の自分の読書からだったか)そうか私たちの生きている地球がそんなに悪い状態なのかと本気で考え、知ったからには知る以前の生活をのほほんとしていてはいけないのだと決意もしたものだ。
あれからとうに30年は経っているというのに、CO²の削減は後手後手になっている。石炭の採掘はもうとうに日本の産業構造から終焉したが、輸入してまで石炭で火力発電所を続けようとしている。原発に至ってはスリーマイル島、チェルノブイリと事故が起こって、次はフランスか日本かと言われていたところ、福島で起きた。それでも再び鎌首をもたげ息を吹き返しつつある。とんでもないことだ。
いい加減、学べよ、人類!
JT生命誌研究館名誉館長の中村桂子さんは「老いを愛づる」という著書の中で「年をとるということは、次の世代に譲っていくということであり、それが生きものらしさなのです。譲るお相手は誰でもよい。もちろん自分の子どもたちが一番良いのでしょうが、それにこだわることはありません。子どもには私の遺伝子がつながっているからとお思いかもしれません。確かにその通りですが、実はほとんどの遺伝子はみんなで共有しているのです。もちろん人間みんなでの共有ですし、生きものみんなの共有でもあるのです。ですから、自分のことだけ考えるのではなく、次の世代の人の誰もが「生まれて生きてよかった」と思えるためのお手伝いをするのが、年を取ったものの役割かなと思います。」と述べていらっしゃる。
類的な役割をまっとうするというスタンスこそ、環境問題には必要だと、最近特に強く感じる。
グレタ ひとりぼっちの挑戦の上映
4月10日(日)ベイサイドポケット ①10:30~②14:30~③8:30~
前売り券大人1,000円 高校生以下500円
当日券大人1,200円 高校生以下700円
未就学児と障がい者とその介助者は無料