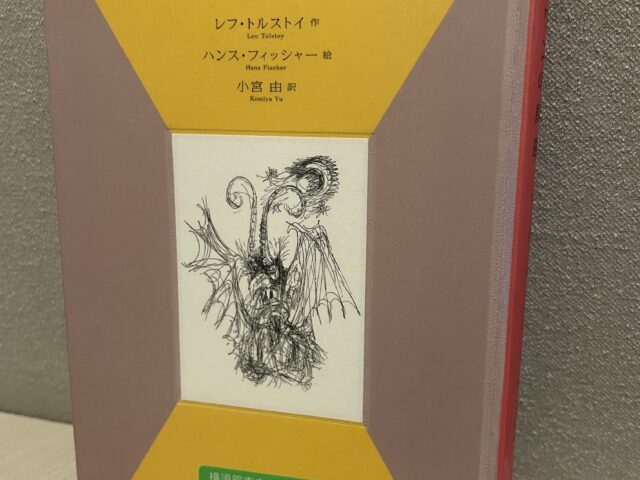アスベストに関する条例への規制緩和の陳情
9月定例議会 都市整備常任委員会に「アスベスト」に関する条例の緩和を求める陳情が出されました。「アスベストの条例」の正式な名称は「横須賀市建築物の解体工事に伴う紛争の未然防止に関する条例」と言います。
陳情ではこの条例の
第3条の(3)のイ 高さ(建築基準法施行令第2条第1項第6号に規定する高さをいう。以下同じ。)が10メートルを超える建築物(以下「中高層建築物」という。)の解体等工事を行う場合は、当該中高層建築物の外壁から敷地までの水平距離が当該建築物の高さの2倍の範囲内にあること。
という文言の高さの2倍が厳しすぎるので緩めるべきというのが第1の趣旨。
もう一つは
第12条 工事業者等は、近隣住民に解体等工事説明ちらし配付後に、説明会等の直接説明を行わなければならない。ただし、説明会等の直接説明ができないことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
という中にマンションの大規模修繕等軽微なものは含めないと謳うべきというのが第2の趣旨。
後者の方では条例の文言に「解体等工事」という言葉があり壁や廊下のひび割れ補修の際等に飛散性アスベストが入っていれば適用となる。これではあまりに縛りすぎではないかというのが陳情者の思いということだと思います。
結論的には、この陳情は「不了承」となりました。私たち日本共産党も含めすべての都市整備常任委員がこの陳情に賛同しませんでした。
しかし、所管の都市部の見解は「今後は部分的に適用基準の緩和を検討していく」というようなニュアンスのもので、いくつかの会派は推移を見守りたいと表明しました。
私の考えは2点あります。
1点目はこの条例が昨年2018年3月から施行されていて、まだ始まって1年半ということ。つまり緩和や見直しという段階でも、推移を見守るという段階ですらないということです。
2点目は解体等におけるアスベストの問題は今後ピークを迎えます。加えてまったく規制がかけられていなかった時期に曝露した方々が今後顕在化してくると見られています。そのようなときに市の条例が緩和の方向に向くということは何を意味するのか。世論との逆行です。緩和を許せば横須賀市の見識が疑われると思います。実際に安全ということと同時に自治体は住民に安心を提供するということもしなければならないと思います。
私の浦賀の事務所に先日相談でお見えになった方は、肺のCT画像を撮って、アスベスト被害であることがわかったそうです。写真は了解を得て撮らせてもたいました。今後はモニタリングをしながら、健康管理をしていくとのことです。
旧平作小学校に給食センターをつくるにあたって、校舎や体育館の解体をすることが決まっていますが、その説明会でも年配の方が「自分はアスベスト被害者」、解体の際にアスベストが飛散しないように十分に対応してほしいと深刻な表情で訴えていました。
横須賀市は造船のまちであったことからも、アスベスト曝露の労働者は潜在的にかなりいるのではないかと思います。
私は一般質問でアスベストを取り上げたことがあります。3年前の12月議会です。
そのときの原稿のダイジェストを記しておきたいと思います。事実のみの列挙です。
・アスベストは耐熱性、絶縁性、保湿性にすぐれ、古くから奇跡の鉱物として重宝されてきた。
・しかし、高濃度のアスベストを長期間吸い込むような作業に従事した労働者に、じん肺や中皮腫の健康被害が起こり、社会問題となった。
・アスベストは、暴露から発症までの潜伏期間が長く、静かな時限爆弾とも言われている。
・現在、アスベストを0.1%以上含む製品の製造、使用は禁止となっている。
・したがって、今後気をつけなければならないのが建物の解体だ。
・環境省の試算では、解体工事の際に排出されるアスベストのピークは2020年から2040年ごろ。その排出量は年間で100万トンとも言われている。
・また、災害時の建物倒壊との関係においても、アスベスト対策は非常に重要。
・1995年に発生した阪神・淡路大震災でも、2011年の東日本大震災でも、アスベスト被害は確認されてる。
・川崎市は、携帯型石綿分析装置、アスベストアナライザーを2台所有している。
こういう状況をみるにつけ、緩和などとんでもない!というのが私の本音です。
引き続き、注視していきます。